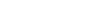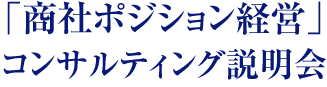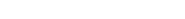マネージ・コンサルティングのコラム


【商社ポジション経営】と間接部門のコスト
会社の部門には、大きく2つあります。
1つは、開発/製造/営業などの会社の売上や利益に直結する「直接部門」。
もう1つは、総務/人事/経理などの売上や利益には直結しない「間接部門」。
より簡単に言うと、稼ぐのが「直接部門」で、その稼ぎを使うのが「間接部門」ということ。
「直接部門」=生産
「間接部門」=消費
と言った方がより理解しやすいかもしれない…。
当然ながら、会社は売上や利益を上げていかなくてはならないため「直接部門」が
重要だということは間違いないが、かといって「間接部門」が重要ではないということでもない。
「間接部門」の働きがあるから、「直接部門」が機能するとも言えるからだ。
しかしながら、現実問題として、会社経営において、言えるのは
「直接部門」が機能しなければ、「間接部門」があっても意味はないということ。
もっと言えば、「直接部門」さえ、しっかりと機能し売上や利益を上げていけば
「間接部門」の働きが良くなかったとしても、会社というのは、成長していく。
むしろ、「直接部門」が大した働きもしていないのに「間接部門」は、大企業並みの
管理体制などになっている会社も少なくない。
また、「間接部門」を食わせる為に「直接部門」が働いているとでも思えてしまうほどの会社もある。
そういう会社というのは、間違いなく、低収益で苦しんでいるし、本来のビジネスの本質から大きく外れた
経営をしているということを意味している。
よく会社経営においての「理想的な直間比率」は、どういう割合なのか!?という話しがある。
7対3 / 8対2 とか(勿論、「直接部門」が大きい)…。
業種や業態規模にもよるだろうが、完全に10対0 は、難しくとも
可能な限り、10対0 に近い状態が望ましいし、高収益会社になりたいのであれば、そこを目指すべきだ。
ちなみに、商社ポジション経営は、間接部門のコストを極限まで下げた経営手法であるため利益が大きい。
つまり、直間比率で言うところの、10対0 を目指せる経営手法である。
商社ポジション経営には、以下の2つの要素がある。
・経営リソースが少なくても元請けポジションをとれる
・価格を決められ、自らが中心となった事業展開ができる
つまり、価格設定権を握れるから高収益会社になれる。